
最大1000km、安全・快適な走行を可能に
電力回生技術の投入で拓く
電動アシスト自転車の新時代
電動アシスト自転車の新時代


太陽誘電は、1回の充電で最大1000km走行可能※な回生電動アシストシステム「FEREMO™(フェリモ)」を開発した。
この業界に革新をもたらす可能性を秘めたFEREMO搭載車として、丸石サイクルが開発したのが次世代電動アシスト自転車「Re:BIKE(リバイク)」だ。電動アシスト自転車の未来と、FEREMOが生み出すイノベーションについて両社のメンバーが語った。
電動アシスト自転車が登場してから30年以上が経過し、今では買い物や子供の送り迎え、通勤通学、シェアサイクルなど、日々の暮らしにあたり前に普及している。
他方で、「生活や社会を支えるモビリティとして、電動アシスト自転車の潜在能力が生かせる利用シーンは、まだまだ未開拓のまま残っていると考えています」と話すのは、丸石サイクルで商品開発を指揮する竹林宏樹氏だ。同社は1894年の創業以来、生活に根差したユニークな製品を提供してきた自転車メーカーである。
「しかし、自転車業界内の力だけでは、社会にインパクトを与えるイノベーションの創出は困難。他業界の斬新な知見やアイデア、先進的技術を生かした製品作りを目指す協業が必須です」(竹林氏)
こうした時代と社会の要請に一層応えるように、モビリティへと電動アシスト自転車の進化を後押しする技術が、太陽誘電の回生電動アシストシステム「FEREMO」である。
FEREMOは、下り坂の走行や減速時に運動エネルギーを電力として無駄なく回収することで、1回の充電で最大1000kmアシスト走行できる、太陽誘電のパワーエレクトロニクス技術の粋を注いで開発した画期的システムだ。アシスト力や電力回生の度合いはユーザーが自在に設定できるため、様々な目的や場面に柔軟に適応できる。度合いはユーザーが自在に設定できるため、様々な目的や場面に柔軟に適応できる。

(左上)FEREMOを搭載した丸石サイクルのRe:BIKE。飽きのこないシンプルでスタイリッシュなデザインを採用。(左下)電力を回生しながら下り坂を減速走行。(右上)前輪に取り付けられたFEREMOの回生システム対応モーター。(右下)消費カロリーや発電量を表示するモニター。健康増進効果や脱炭素への貢献を客観的数値で可視化。
FEREMOを開発した太陽誘電の保坂康夫氏は「人に寄り添い、様々なシーンで気軽に利用できることこそが、自転車の存在価値だと考えています。FEREMOの名称は『Future Energy Recycling system for Mobility』の頭文字から。生活の中での快適な移動や、景色を楽しみながらの走行、無理のない健康増進などに利用いただくために、必要な機能と性能を徹底的に洞察し、部品レベルから盛り込みました」と話す。
丸石サイクルは、太陽誘電のFEREMOを採用した電動アシスト自転車「Re:BIKE」を開発し、販売を開始。開発に携わった同社の鈴木仁氏は、「電池残量を気にせず長く走行できる特長を際立たせるために、より多くの場面で利用できる、丈夫で飽きのこない、シンプルでスタイリッシュなデザインを採用しました」と語る。Re:BIKEを先駆けとして、FEREMO搭載車を目にする機会が増えそうだ。
――なぜ丸石サイクルが異業種である太陽誘電のシステムの採用に至ったのでしょうか。
保坂:太陽誘電には、様々な事業や技術を通じて、社会課題の解決に貢献したいという強い思いがあります。2000年代の中ごろより、長年蓄積してきた当社の電源回路技術と知恵を生かした、社会的価値の高い開発テーマがないかと模索を続け、その一つとして注目したのが電動アシスト自転車向けの回生技術でした。
ただし、自転車は乗り心地などユーザーの主観で価値が評価される商品です。当社はBtoB事業をメインにしており、自転車ユーザーとの接点も無く、そうした観点からの知見がありません。この点が、応用展開と技術改善を進める上での課題でした。そして、活路を開くための一つの方策として、東京サイクルデザイン専門学校に、開発した回生電動アシストシステムを教材として提供することにしたのです。そこで当時学生だった、現在丸石サイクルに在籍する鈴木さんに知っていただいたのもきっかけの一つです。

鈴木:電動アシスト自転車を設計するスキルの需要は高まっています。当時、学校側も密な意思疎通ができて技術力も高い企業からの支援は渡りに船だったようです。
竹林:その点では丸石サイクルとしても同様です。電動ユニットは電動アシスト自転車の価値の源泉であり、より良い製品を生むためには、部品レベルからの作り込みが欠かせません。自転車メーカー内では開発できない高度な技術を導入し、なおかつ技術支援や改善要求などの密な連携を繰り返すことで、優れた製品を早期に市場投入できるようになります。
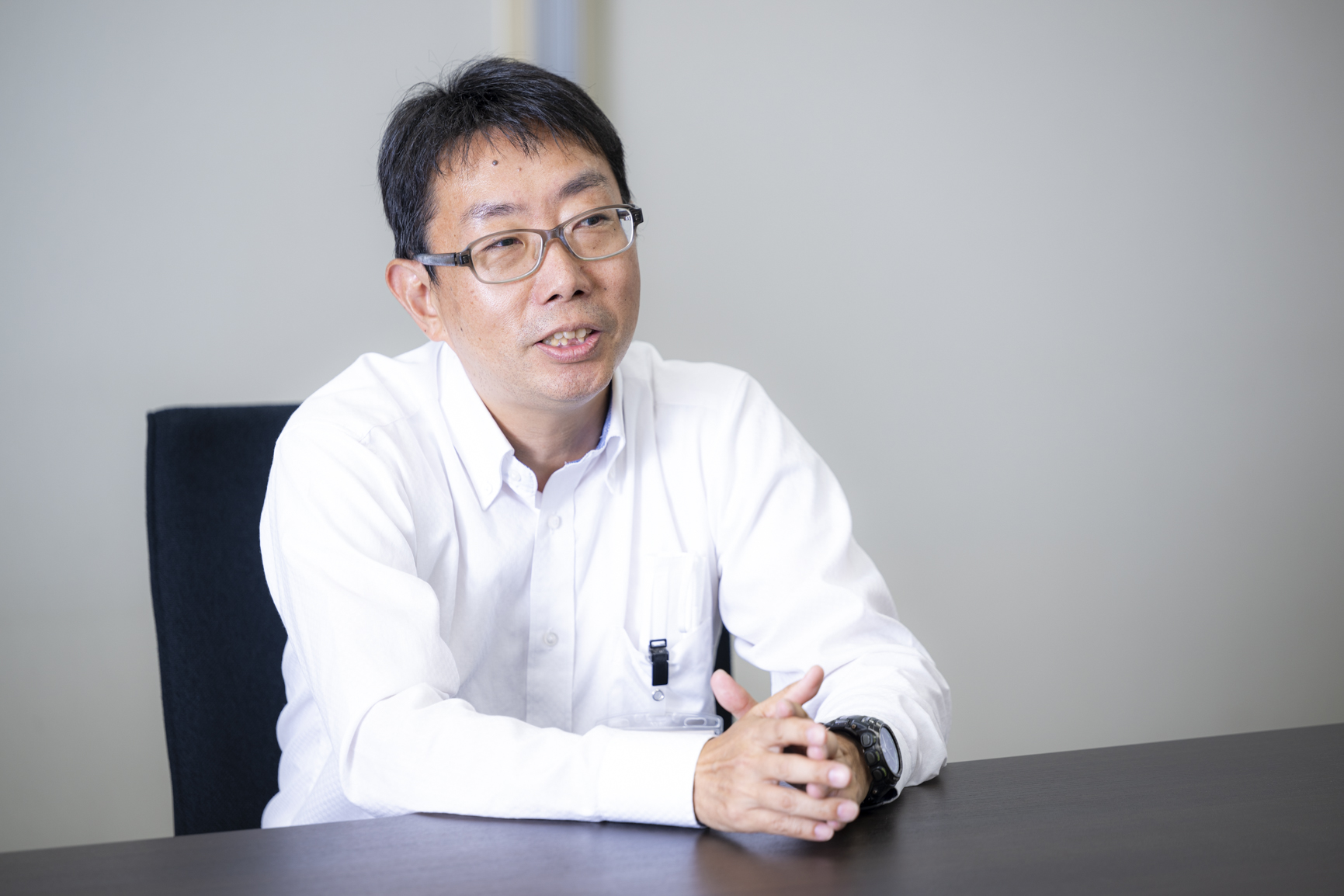
――自転車用の回生技術と、ハイブリッド車など自動車に導入されるそれとの違いは何でしょうか。
保坂:自転車用の回生技術では、機能を利かせることで、ユーザーがどのように快適・便利に感じるかが重要です。利用者一人ひとりの感覚・感情・状態に応じた千差万別な回生機能が求められます。この点が、エンジン負荷を客観評価して回生効率を最大化できる自動車用との最大の違いです。
竹林:1回の充電で最大1000km走行できるカタログ上の仕様もさることながら、自転車の価値評価では漕ぎ味や乗り味などユーザーの感覚に訴える質の高さが重要になります。FEREMO自体にこの点に配慮した技術が投入されています。その潜在能力を引き出して爽快に乗れる自転車に仕上げるところが私たちの腕の見せ所です。
――FEREMOによって、電動アシスト自転車の利用シーンはどのように変わっていくでしょうか。
鈴木:自転車は、自分で漕がないと動かないためか、不思議な達成感がある乗り物です。旅先での観光などに利用すれば、自転車で回った思い出は心により深く刻まれるように感じます。FEREMO搭載車は、移動を快適にしながら、自動車やバイクなどでは得られない体験を提供できます。
竹林:近年、シェアサイクルでは、充電頻度などを含め管理の難しさが課題にあがっていましたが、充電サイクルを減らせるFEREMO搭載車はこれを容易にします。Re:BIKEなら、1日5kmの走行と仮定すると、充電スパンは200日です。インバウンド向けなどで、これまで以上に多くの来訪客に快適なサービスを提供できそうです。

保坂:既に能登半島地震の被災地にFEREMO搭載車を寄贈させていただきました。また、FEREMOには、消費カロリーや発電回収した電力を数値表示するモニターを盛り込んでいます。健康増進への達成感や脱炭素への貢献を可視化することで、利用者が充実感を感じられることを期待しています。
――今後のビジョンをお聞かせください。
鈴木:自転車は、先進国から途上国まで世界中で利用される利用者層が多様な乗り物です。FEREMOによるイノベーションの効果は、世界に広がる可能性があると感じています。
竹林:Re:BIKEは、先進的なモノを求める“アーリーアダプター”が自慢できる自転車として仕上げました。FEREMOは、電動アシスト力を最大化したパワーモードでも100km走行可能です。こうした点に注目すれば、さらに広い応用を拓けるのではと考えています。より多くのユーザーが利用したいと感じる、多様な自転車を開発していきます。
保坂:FEREMO搭載車は、発電機能を持っています。この特長を生かせば、普段はフィットネス感覚で健康増進にも役立ち、災害などの停電時には、発電機とポータブル電源としても有効利用できると考えています。