社長メッセージ
つながる社会の
発展に貢献し、
経済価値と社会価値の
拡大を目指します
代表取締役社長
登坂 正一
目指す姿
ミッションが着実に浸透
太陽誘電は、2020年に創立70周年を迎えました。それを機に、30年後の100周年、さらにその先においても社会に貢献できる企業であるため、2021年にミッションとして「おもしろ科学で より大きく より社会的に」を定めました。これは、従前から太陽誘電が進むべき方向を示す言葉として受け継がれてきた「より大きく より社会的に」という言葉に、「おもしろ科学」を加えたものです。「おもしろ科学」には、2つの想いを込めています。1つは、太陽誘電が展開している事業を支える源泉が科学そのものであり、その中にはわくわくする体験や思いがけない発見、驚きなどとの出会いがあるという意味です。もう1つは、会社が存続していくためにはまず従業員が仕事をおもしろいと思わないと始まらないという想いです。従業員には、これらを日常的に意識しながら仕事を進めてほしいと願っています。
このミッションを掲げてから1年が経過し、「自分にとって“おもしろ科学”とは何か」「自分の仕事を通して“おもしろ科学で より大きく より社会的に”を実現するにはどうしたらよいか考えた」という声が聞こえるようになりました。ミッションが従業員の意識の中に着実に浸透していると実感しています。
事業環境の変化
世の中のDXが進展し、部品需要が拡大
5Gや自動車のCASEなどさまざまな分野でデジタル技術が進化する中、2021年に60兆円規模だった半導体市場は2030年には100兆円規模にまで成長することが見込まれています。新型コロナウイルス感染症の流行など景気を減速させる事象もありますが、リモートワークによる電子機器の需要増などの機会も生まれており、世の中は着実にDX化という方向に動いていると思います。自動車のxEV化の加速や通信データ量の増大に伴うデータセンターの拡大に加え、電力消費抑制のために電源の効率化も進んでいます。そこに使われる半導体を動かすために、コンデンサなどの電子部品は欠かせないものであり、増加する需要に対応できるように供給能力を拡大していきます。
新型コロナウイルス感染症の世界的な流行は収束方向に転じていますが、感染拡大防止のため大規模なロックダウンを実施する地域があるなど、いまだ予断を許さない状況です。引き続きステークホルダーの健康と安全を考慮し、BCP(事業継続計画)に基づいて各種対応策を実施しています。生産拠点では、各国政府・自治体の指示・指導に従い、感染防止策を徹底して安定操業に取り組んでいます。生産部門以外についても、地域の状況に応じて在宅勤務制度などを導入し、スムーズな事業運営に努めています。また、今年に入り地政学リスクが増大していますが、ロシア・ウクライナ両国に太陽誘電グループの拠点や主要な顧客・サプライヤーはなく、両国向けの売上は僅少です。このため、太陽誘電の事業活動に対する直接的な影響は軽微ですが、調達・物流コストの上昇や物流リードタイムの長期化などが発生しています。
今後も大規模な自然災害をはじめ、予期せぬ外部環境の変化は世界各地で発生するでしょう。どのような状況でも安定した事業活動を継続できるように、さまざまな情勢を勘案しつつ対応していきます。
中期経営計画2025
1年目は業績目標を達成、ESG活動の一部に課題が残る
2021年度にスタートした中期経営計画2025は、10年後の2030年からバックキャストして策定した5年計画です。計画初年度の2021年度は、売上高が前年度比16%増の3,496億円、営業利益は67%増の682億円で、増収増益を達成しました。旺盛な需要や商品価格の値下がりが緩やかだったこと、為替影響がプラスに働いたことなどにより、期初計画を大きく上回りました。その結果、売上高は5年連続、営業利益は3年連続、経常利益と当期純利益は2年連続で過去最高を更新しました。中期経営計画2025では、売上高、営業利益率、ROE、ROICの4つを経済価値に関する経営指標としていますが、売上高以外は目標を達成し、好調なスタートを切ることができました。
一方、社会価値向上のためのESG活動においては、GHG排出量、水使用量、新卒女性採用率は目標を上回る水準となりましたが、廃棄物、傷病率・度数率、ワークエンゲージメントの指標は目標に届きませんでした。今後、需要の伸びに対応して生産能力を増強していく方向において、環境への負荷低減や安全性の向上、従業員の働く意欲向上などは、一層取り組みを強化していく必要があります。中期経営計画2025の1年目を終えて、やるべきことがより明確になりました。それぞれの計画未達の要因を分析して対策を講じ、今年度以降取り組みを加速してキャッチアップしていきます。

事業戦略
注力市場の開拓について
太陽誘電は成長領域として、自動車、情報インフラ・産業機器を注力市場とし、それらが売上全体に占める比率の目標を50%に設定しています。2021年度はすでに46%に到達しました。ここ数年の収益性の推移を見ると、注力市場拡大の効果により着実に安定性が増してきています。今後、太陽誘電の主力商品である積層セラミックコンデンサ(MLCC)では自動車のxEV化で需要拡大が期待できる高耐圧品のラインアップ拡充、インダクタでは自動車やデータセンター、メモリへの展開といったように、顧客が求める特性に対応する商品ラインアップの拡充を図るなど目標の50%に向けて取り組んでいきます。
製品別(コンデンサ、インダクタ、通信デバイス)の状況
顧客からの要望に着実に対応していくためには、商品展開と生産能力増強の2つが、一番必要で注力しなければならないことです。商品開発については、根幹の要素技術である材料技術と積層技術の高度化を図っています。中長期的な視点での研究開発活動を展開しており、突然訪れるセレンディピティ(偶然の産物)による技術的ブレークスルーを実現できるよう取り組みを続けています。
MLCCについては、群馬県の八幡原工場に材料棟(2022年12月竣工予定)、マレーシアのTAIYO YUDEN (SARAWAK)と中国の太陽誘電(常州)電子に新工場(いずれも2023年6月竣工予定)を建設中です。市場が毎年10%程度伸びると見込まれる中で、市場の伸びを上回る10-15%の能力増強を継続していきます。これと並行して、生産性改善活動「smart.E」に引き続き注力しています。好事例をグループ内に水平展開できる仕組みを構築するなどして、歩留まり改善を中心とした生産性向上によって、実質的な能力増強につながる努力を続けています。
インダクタでは、現在の主要市場であるスマートフォン以外でも拡大を目指し、メタル材料/フェライト材料と積層構造/巻線構造の組み合わせで顧客ニーズに合った商品を展開することにより、市場・顧客の多様化を推進しています。2021年度は情報機器、自動車、情報インフラ・産業機器向けが拡大しており、今後もさらなる用途拡大を進めていきます。
通信デバイスにおいても、メイン市場であるスマートフォン向けに加え、自動車のテレマティクス用途やM2M、IoT市場において、フィルタの堅牢なパッケージ構造による高信頼性を高く評価していただいており、幅広い用途への展開を目指しています。
新事業の創出
社会課題解決型ソリューションの創出を推進
新事業は、「人に寄り添う」ソリューションを提供するというのを1つの大きな指針としています。太陽誘電の独自技術と社外のリソースを融合し、機器の提供にとどまらず、それを活用したソリューションを含む提案で、社会課題解決型の事業展開を目指しています。
すでに事業化を実現した電動アシスト自転車向けの回生電動アシストシステムは、環境負荷の少ないニューモビリティとして評価され、サイクリング志向も相まって好調に売上を拡大しています。この他にも、河川モニタリングシステム、スマートメーター向けのLTEモジュール、IoTソリューションsoliot™による位置検知ソリューションなどの事業化に向けて取り組んでいます。河川モニタリングシステムは、かつて太陽誘電が独自開発した光記録メディア技術を応用したミリ波センサを使用した電波式水位計などで構成されるもので、群馬県や広島県の各地で実証実験を展開しています。
新事業に対するスタンスとしては、さまざまな社会課題(ニーズ)と太陽誘電の技術(シーズ)とのマッチングや将来の需要予測、競合環境などを考慮した評価プロセスを体系化し、事業化が見込めるテーマを選択しています。経済価値、社会価値の向上に寄与できるものを厳選しながら新事業創出を進めていく考えです。
ESG戦略(環境)
GHG排出量の削減目標を上方修正

太陽誘電は、「国連グローバル・コンパクト(UNGC)」に署名し、「人権」・「労働」・「環境」・「腐敗防止」の4分野からなる10原則を強く支持しています。サステナブルな企業活動を重視し、ESGに関する取り組みを強化しており、中期経営計画2025においては経済価値指標だけでなく社会価値指標も定めています。中でも環境関連ではGHG排出量削減と廃棄物、水使用量の削減を指標に設定しています。
GHG排出量については、2021年のCOP26※において合意された「1.5℃目標」の達成に貢献できるように、2030年までのロードマップを再検討しました。その結果、中期経営計画2025のスタート時に設定した25%削減(2020年度比)という目標を、42%削減へと上方修正しました。
太陽誘電はものづくりの会社であり、まずやるべきことは省エネです。生産活動において、ロスを限りなく少なくすることに注力していきます。材料開発に代表される数々のコア技術を高度化し、単位あたりの取れ高を上げることが省エネに直結します。その次が創エネ・再エネという順序で考えており、一例がR&Dセンターを2024年度までに100%再エネ化することです。太陽光発電と蓄電池を設置して創エネに取り組むとともに、不足分は再エネ電力に切り替えます。また、中国・マレーシアに建設中の新工場についても、環境対応型にするなどの施策を推進しています。グループ全体で、脱炭素社会実現に向けて省エネ・創エネ・再エネのものづくり体制を構築するとともに、TCFDに関連する情報開示なども拡充させていきます。
※COP26:国連気候変動枠組条約第26回締約国会議
ESG戦略(人材)
女性管理職比率を新たに目標として設定
従業員が健康で、仕事で活力を得てイキイキと能力を発揮できること。これが太陽誘電の価値創造の源であると考え、人材への取り組みを重視しています。中期経営計画2025では、新卒女性採用率30%以上を目標として設定していますが、2022年度からはこれに加え、女性管理職比率10%以上という目標を新設しました。これまでの積極的な女性採用や人材育成が順調に進んだことで、女性管理職候補者の母集団拡大が進み、管理職についても目標を設定しそれにコミットすることで取り組みが加速できるとの考えに基づいたものです。
また、ワークエンゲージメント2.5以上という目標を立てていますが、2021年度実績は2.25で未達となりました。これについては、ミッションに込めたような仕事のおもしろさ、やりがいについて、従業員がまだ十分に実感できていない状況なのだと捉えています。業務の進め方やコミュニケーションなど関連する課題をしっかり分析し、今後の対策によって目標達成に近づけていきたいと考えています。
ESG戦略(ガバナンス)
社外取締役を中心とした諮問機関の活用
コーポレートガバナンスは、企業の長期的・持続的な成長の土台です。コーポレートガバナンス・コードの各原則を実践し、ステークホルダーとの対話などから得た知見を取締役会で共有・議論して、経営に反映していくことを基本にしています。
太陽誘電は、コーポレートガバナンス・コードの制定前から社外取締役を委員長とした指名・報酬委員会を任意に設置し、取締役の指名と報酬というコーポレートガバナンスの要ともいえる重要な課題に取り組んでいます。2021年度は、報酬委員会を中心に役員報酬制度の見直しを行いました。
一方、指名に関しては、2022年2月に実施した取締役会実効性評価において、中長期視点での取締役会の構成のあり方についての議論が必要であると認識しています。その時々の経営方針・経営戦略に照らして最適な取締役会構成とするために、指名委員会を中心として次世代のCEOおよび取締役候補者を計画的に育成していくことがより必要になっていると考えています。
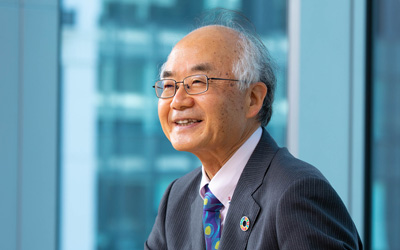
おわりに
太陽誘電は、「おもしろ科学で より大きく より社会的に」というミッションのもと、中長期の事業環境を見据えて中期経営計画2025を策定しました。経済価値とともに社会価値に関する目標も設定し、これら2つの価値向上を両立する経営によってさらなる飛躍を目指します。そのためには、株主の皆様、お客様、従業員、地域社会など、ステークホルダーの皆様からの信頼とご協力が不可欠です。引き続きご支援をいただけますよう、お願い申し上げます。
