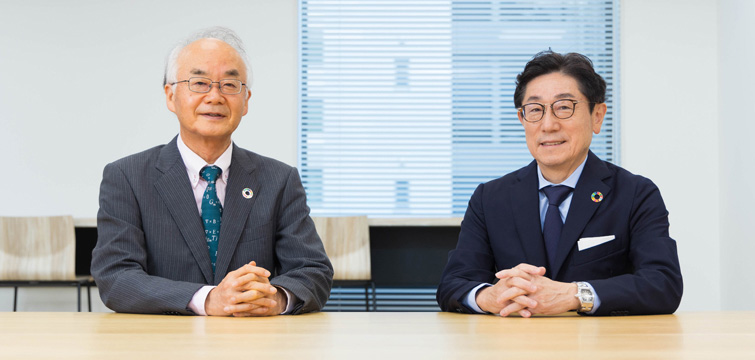会長×指名委員会委員長 対談
新社長の選任に関して
太陽誘電は2023年6月に社長交代を実施し、取締役専務執行役員の佐瀬が代表取締役社長執行役員(以下、社長)に、代表取締役社長を務めた登坂は取締役会長に就任しました。会長の登坂と社外取締役で指名委員会委員長の平岩氏の両名が、今回のサクセッションの進め方や佐瀬新社長への期待などについて対談しました。
-
取締役会長
登坂 正一
-
社外取締役
指名委員会委員長平岩 正史
社長在任期間を振り返って
登坂:私が社長に就任した2015年度は、売上高2,403億円、純利益147億円でした。その後、自動車向けを中心に積層セラミックコンデンサなど太陽誘電が手掛ける製品の需要増加の時期が続いたことから成長軌道に乗り、2021年度には売上高3,496億円、純利益543億円まで拡大しました。
社長就任後は、「3つのモノ」と「1つのコト」に集中するという方針を立て、事業の選択と集中を進めてきました。モノというのは、コンデンサとインダクタ、通信デバイスという電子部品事業であり、コトというのは、ソリューションによる新事業創出です。電子産業における付加価値構造を表すスマイルカーブの考え方を重視し、カーブの両極端で付加価値が高いとされるモノとコトに集中し、それまでやっていた実装・組み立てなどは縮小させていきました。自動車を中心とした需要の追い風を捉えること、モノとコトへの集中、この2つにこだわったのが、私の社長在任期間です。世の中が大きく変わる中で、ある意味、太陽誘電は気合と根性でここまでやってきたというのが本音のところです。
平岩:登坂さんはそうおっしゃるが、私はそれだけではなかったと思います。私は弁護士としてさまざまな会社のガバナンスを見てきましたが、太陽誘電のガバナンスは私が社外取締役になる前から、しっかりしていたと思います。私が就任した2016年6月には、すでに社外取締役が2名在籍していましたし、私と同時に社外監査役に就任された吉武さんは、常勤の社外監査役という非常にユニークな存在です。そういう意味では、気合と根性でいくことの裏側に、ちゃんとブレーキをもった体制を作って会社を運営してきたということを常に感じてきました。
登坂:ただ、太陽誘電がこの先も大きく成長していくことを考えると、次の社長は、もっとロジカルに会社を動かしていく人がいいと考えていました。それが今回の社長交代における候補者選定の考え方につながっています。
具体的な選任プロセス
平岩:社長交代にあたって、私は指名委員会の委員長という立場で関わりましたが、振り返ってみると、2018年に策定した後継者計画に従って粛々と進めてきたといえるでしょう。社長である登坂さんが取締役の中から候補者を指名して、その候補者を育成するというやり方で進めました。候補者の資質を見極めた上で、必要な経験などを積んでもらうというプロセスを踏みました。
登坂:私も、社長になった時点で、何年か後には社長交代がある、すなわち、そこに向けて次の社長にふさわしい人物を選ぶ必要があるということを強く意識しました。その時に考えた社長にふさわしい人物というのは、単に資質だけでなく、社長を務めるのに必要な経験を積んでいるということもあったわけです。
そういう意味で、佐瀬さんは事業の経験が長く、事業については知り尽くしている一方で、経営企画、財務といった経験が不足しているのは明らかでした。私もそうでしたが、管理、財務といった経験が不足していると社長になった後に非常に苦労する。そういう意味も込めて、社長就任までの直近の3年間は経営企画本部でさまざまな経験をしてもらいました。
平岩:指名委員会では、資質を見極めるために面談を複数回実施しました。佐瀬さんとは3回以上、他の取締役ともそれぞれ2回は面談する機会を設けました。その面談で、これからの太陽誘電はどうなるかという議論をさせてもらいました。その中で、我々なりに今後を理解するというセッションがあったのがすごく特徴的でした。このセッションで、佐瀬さんの考え方を理解することができ、彼で間違いないということが確信できました。
佐瀬社長のキャラクター
平岩:指名委員会委員長としての面談で、「経営理念の3つを変えるつもりはありますか」という質問をした時の回答が印象に残っています。企業理念は、いつまでも同じでなくてもいいわけですよね。社長交代のタイミングで企業理念を変えていく、キャッチフレーズを変えていく、こういうことも会社によってはよくあることです。
私の質問に対して、佐瀬さんは「自分はそういうカラーではない。今あることをきちんとこなしていく」と答えました。さらに「論理的に物事を進めていって、できることとできないことをはっきり振り分けながら会社を成長させていく」と強調されました。
太陽誘電の現在は、新たに何かを生み出すステージというよりは、目指すべき姿は明確であり、それを達成できるかどうかが重要という局面にあります。佐瀬さんの答えは、太陽誘電の今に最も適した答えであり、そのような考えでいるのならば、今の時代の太陽誘電の社長に適していると思いました。
登坂:会社は社長のキャラクターによって大きく変わることもあると思います。そういう意味でいうと、私と佐瀬さんの最大の違いは、私は気合と根性、感性で生きているのに対して、彼は合理主義者ということです。
私は、世の中が非常に変動する中で、同じようなタイプの人間が社長を継承するのはきっと良くないだろうと考えてきました。違うタイプの人間が社長になったほうが会社としての多様性も発揮できるのではないかと思いますので、経験、資質だけでなく、そういうキャラクター面でも佐瀬さんには期待しています。
平岩:登坂さんは違いを強調されますが、私から見ると、登坂さんにも佐瀬さんにも共通して言えるのは、基本的に良い意味で頑固だということです。周りの意見をいろいろ聞くという人もいますが、私の経験の中では、社長になる人は頑固でぶれない人が多い。登坂さんと佐瀬さんはスタイルこそ違うものの、ぶれない、という点ではすごく似ていると思うことが多々あります。そういう意味では二人の持つキャラクターは、本質は同じなのかなとも感じています。
今後の選任のあり方について
登坂:今回の社長交代にあたって、私の立場は非業務執行の取締役会長となりました。今後の私の役割は、中立的に物事を判断し、ガバナンスを効かせていくことにあると考えています。
今までは業務執行を兼ねていたことから、どちらかといえば執行側に寄って考えていましたが、今後は、執行機能を持たないが社外取締役よりも社内のことを知っている取締役として、コーポレートガバナンス強化を中心に働きかけていきたいと思っています。私がそのような役割を引き受けることで、佐瀬社長にはさまざまな執行における課題に専念してもらいたい。特に、中期経営計画2025とその先の成長に向けた絵を描くことに注力してもらいたいと考えています。
平岩:今回の社長交代というサクセッションプランは適切に実行できたと考えていますが、今後の経営TOPの交代をより良いものとするためには、選択の母集団をどうやって増やしていくかというテーマも検討する必要があると考えています。すなわち、一般論的には母数が多いほうが、選択肢が多くてメリットがあるということは明白ですので、その意味で、今後のサクセッションプランにおいては、どのように選択肢を確保していくかは非常に重要なテーマだと思っています。太陽誘電の後継者計画では、代表取締役社長執行役員は業務執行取締役の中から選ぶことが前提となっていますが、選択肢確保には執行役員の段階を含めて候補者を見ていく必要があるかと考えます。
指名委員会は、執行役員の指名の時も面接をして選びますが、候補者がどのような人物なのか、よほど特定の接点がない限り分からないのが現状です。今、太陽誘電でサクセッションプランと呼んでいるのは経営層に限定されていますが、より良いマネジメント層の形成に向けては、執行役員になる前の段階から、一定の人材プールを作っていくことが必要かと思います。これについては、中期経営計画2025の中でも、人材開発の加速というテーマで進められつつあります。もう1つは、外からの人材採用を加速していくことが大切です。この2つの道は言わば王道ですが、それを着実に進めていくことが必要です。まさに太陽誘電ではそれをやろうとしている。それは非常に評価できると考えています。